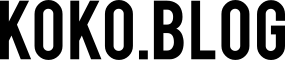なぜ、無能な人ほど権力にすがりつきたくなるのか?

目次
- 1. 総論:なぜ「無能な人」ほど権力にしがみつくのか
- 弱さを隠すための“盾”としての権力
- ポイント
- 2. 自分の弱点に気づけない問題
- 「分からないことが分からない」
- ポイント
- 3. 不安ゆえのマイクロマネジメント
- 「全部オレが見ないと不安」
- ポイント
- 4. 評価から逃げるための“見えない化”
- 数字や記録を嫌うサイン
- ポイント
- 5. 「声が大きい人」が出世しやすいワナ
- 見かけにだまされる評価
- ポイント
- 6. 権力が人を“鈍く”する
- 思いやりが下がり、勘に頼りがち
- ポイント
- 7. こういう上司との関わり方
- 自分を守り、仕事を前に進めるコツ
- ポイント
- 8. そのような人の“末路”
- 短期は得しても、長期で信頼を失う
- ポイント
- 9. まとめ
- 弱さを隠すより、事実で強くなる
- ポイント
- 関連
1. 総論:なぜ「無能な人」ほど権力にしがみつくのか
弱さを隠すための“盾”としての権力
職場には、成果は少ないのに、やたら決定権やハンコを集めたがる人がいます。
なぜでしょう。
人は不安になると、自分でコントロールしている感覚を求めます。
力が足りない人ほど、その不安が強く、「自分が決める側」に回ろうとします。
さらに、人は自分の力を正しくはかるのが苦手で、「できていないこと」に気づきにくい心のクセがあります。
その結果、「権力を持てば安心できる」「上にいれば自分の弱さを見られにくい」という考えに引っぱられます。
周りの仕組みも影響します。
声が大きい人や即断する人を「できる人」と見てしまう会社では、こうした人が出世しやすく、余計に権力へ固執しやすくなります。
原因は個人だけでなく、会社の評価のしかたにもあります。
相手を責めるだけでなく、事実で話し合えるルールづくりが必要です。
ポイント
- 不安をおさえるために「決める側」に回りたくなる
- 自分の実力を高く見積もる心のクセが後押し
- 会社の評価のズレが、権力にしがみつく人を増やす
2. 自分の弱点に気づけない問題
「分からないことが分からない」
自信満々なのに中身があやしい…そんな人、見たことはありませんか。
人は経験が少ないほど「どこが難しいか」をつかみにくく、自分を強く見せがちです。
会議で専門家の意見を軽く扱う、あいまいな指示を出す、失敗すると部下のせいにする。
こうした行動は、弱さを隠したい気持ちから出ます。
また、自分に都合のよい解釈をしやすい「自分を守るクセ」も働きます。
これらは誰にでも起こり得ることで、だからこそ“数字や記録”で現実を確認する仕組みが大切です。
思い込みが続くと、同じ間違いがくり返されます。
やったこと・決めたことを記録し、後で見直すだけでも、現実を見る助けになります。
ポイント
- 未経験ほど難しさをつかみにくい
- 都合よく解釈してしまうのは人のクセ
- 記録と振り返りで思い込みを減らせる
3. 不安ゆえのマイクロマネジメント
「全部オレが見ないと不安」
細かい承認や報告を何度も求める上司に疲れたことはありませんか。
力不足の人ほど、不安を減らすために「細かく口を出す」行動をとります。
ルールや書類を増やし、何でも自分を通す仕組みにします。
本人は安心しますが、現場のスピードは落ち、ミスも増えます。
これは「不安→もっと管理→さらに不安」という悪循環です。
「どこまで上げるか」を先に決め、書式もそろえましょう。
たとえば「金額●万円以上は上司承認」「根拠リンクは1枚に集約」など。
境界が決まれば、無駄な往復が減ります。
ポイント
- 不安が強いほど細かく管理したくなる
- 口出しが増えるほど現場は遅くなる
- 境界と書式を決めて往復をへらす
4. 評価から逃げるための“見えない化”
数字や記録を嫌うサイン
うまくいった話だけ強調し、失敗は「外部のせい」にする人がいます。
成果が見えるほど弱さがバレます。
だから、KPIをころころ変える、会議で口頭だけで決める、意思決定の根拠を共有しない。
といった「見えない化」が進みます。
これでは学びが残りません。
「事実を残す」を合言葉にしましょう。
決定の理由、比較した案、かかったコストを、1つのドキュメントに残すだけで十分です。
誰でも読める場所に置けば、責任の押しつけ合いも減ります。
ポイント
- KPI変更・口頭主義・根拠非公開は要注意
- 決定理由と比較案を1枚にまとめる
- 共有の場に置き、検証できる形にする
5. 「声が大きい人」が出世しやすいワナ
見かけにだまされる評価
ハッキリ話す人=有能、ではありません。
人は目立つ特徴に影響されます。
よく通る声、即答、大きな身ぶり。
これだけで「頼れそう」と感じてしまいます。
こうした評価のズレで、実力の限界まで昇進し、そこで止まる人が出ます。
さらに、自分に従う人だけを引き上げると、反対意見が消え、チームは弱くなります。
役割ごとに“何で評価するか”を明らかにしましょう。
管理職は「人を動かして成果を出す力」で見る、などです。
ポイント
- 見かけで実力を判断しやすい
- 従う人だけを上げると組織が弱る
- 役割ごとの評価基準をはっきりさせる
6. 権力が人を“鈍く”する
思いやりが下がり、勘に頼りがち
立場が上がるほど、現場の苦労に気づきにくくなります。
決める立場が長く続くと、他人の気持ちや制約に目が向きにくくなります。
数字だけを見て、実行の大変さを軽く考えてしまうのです。
成功体験が多いと「自分の勘は当たる」という思い込みも強まります。
補正するには、反対意見を歓迎するルールや、小さく試す仕組み(お試し導入→結果で判断)が役立ちます。
「考え」と「実行」を別の場でチェックし、少人数のテストを挟むと、机上の空論を防げます。
ポイント
- 立場が上がるほど共感が下がりやすい
- 勘に頼りやすいので小さく試す
- 反対意見を歓迎する場をつくる
7. こういう上司との関わり方
自分を守り、仕事を前に進めるコツ
相手を変えるのはむずかしい。
だからこそ、自分の守りと進め方を整えます。
まず境界を決めます。
「●万円以上は承認」「報告は毎週●曜に1枚」など、ルールを先に出して合意を取ります。
次に提案の形を工夫します。
「A/B/Cの3案+おすすめ+リスク+次の確認方法」のセットで出すと、不安のタネ(分からないこと)を先に消せます。
記録は短く、見やすく。
決定理由・期限・担当を1枚にまとめ、リンクで共有。感情的な言い合いは避け、事実と手順だけを書くと、相手もたたきにくくなります。
味方づくりも大切。
法務や経理、PMOなど“事実に強い部署”とつながり、個人戦にしないことがコツです。
「無駄な往復が減る」「責任の押しつけ合いが減る」「自分の心の消耗が減る」という3つの効果が出ます。
ポイント
- 境界(上げる条件・頻度・書式)を先に決める
- 提案は選択肢+リスク+確認方法で
- 記録は短く1枚、共有リンクで残す
- 事実に強い部署を味方にする
8. そのような人の“末路”
短期は得しても、長期で信頼を失う
権力にしがみつく人は、最後どうなるのでしょう。
短いあいだは、周りが逆らいにくく、うまくいっているように見えます。
でも、数字や記録を避けるやり方では、学びが残らず、同じミスが続きます。
優秀な人ほど離れ、チームの力は落ちます。
すると、さらに権利でしばろうとして、余計に回らなくなります。
会社にとっても、判断が遅れ、チャンスを逃し、信頼が下がります。
最後に残るのは「肩書はあるけど、誰も本気でついてこない」状態です。
これは本人にも会社にも不幸です。
事実に向き合い、学べる仕組みを作れないと、ゆっくりと行き詰まります。
ポイント
- 学ばない組織はゆっくり弱る
- 人材が抜け、判断が遅れ、信頼が落ちる
- 肩書だけ残って、実質的な力を失う
9. まとめ
弱さを隠すより、事実で強くなる
権力にしがみつく行動は、「不安」「自分を高く見てしまうクセ」「会社の評価のズレ」から生まれます。
だから、個人の工夫と、仕組みの工夫を両方やるのが近道です。
個人では、境界・提案の形・記録・味方づくり。
仕組みでは、役割ごとの評価、意思決定の記録、失敗から学ぶルール。
これだけで空気は変わります。
相手がすぐ変わらなくても、自分とチームの消耗を減らし、成果を守れます。
弱さを隠すより、事実を積み重ねる方が、長く強いのです。
ポイント
- 行動の元は「不安」と「評価のズレ」
- 個人:境界・提案・記録・味方
- 仕組み:評価の明確化・決定の記録・学ぶ習慣
- 事実に立つ人とチームが、最後に強くなる
本ブログでは、様々なネタの記事や自分が気になったことやガジェット等を書いていこうと思っています。
また、データコンテンツ販売も行っています。
WEBサイト制作やポスター制作時にお使いください。
▼koko-box(ココボックス)
https://koko-box.com/